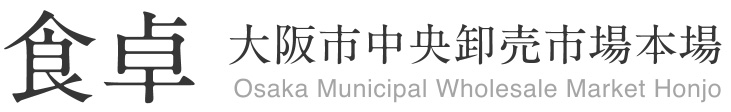旬の食材
 概ね魚は、からだが大きくなる方が、脂ものっておいしくなるものですが、このイサキは、どの大きさでも、とてもおいしいのが特徴です。
概ね魚は、からだが大きくなる方が、脂ものっておいしくなるものですが、このイサキは、どの大きさでも、とてもおいしいのが特徴です。「初夏の魚」のイメージが強いですが、実際、3月~6月頃が一番おいしいのです。特に5・6月の刺身は絶品です。
イサキのもう一つの特徴は、骨がかたく、又、背ビレが尖っていることです。充分気を付けて調理して下さい。刺身以外に、塩焼き・唐揚・ソテーなどの調理方法があります。フレンチやイタリアンにもよく登場する魚ですが、さっぱりした白身魚なので、応用範囲は広いです。かおり高いキノコ類との相性も良いですし、動物性・植物性どちらの油とも良く合います。
当ホームページでも、バターや生クリーム・ブルーチーズを使ったイサキの洋風料理をご紹介しています。アスパラガス・フルーツトマトと一緒に盛り合わせた、ブルーチーズのソースが良く合う一品です。初夏の一日、キリっと冷えた白ワインとの相性も抜群です。

サルエビだったり、アカエビだったりするのですが、獲れるところが同じで、見た目も味も良く似ているので、区別なく出荷されているようです。
旬は産卵期の初夏から秋にかけてで、これからがおいしい季節です。簡単でおいしい食べ方は、唐揚げです。高温の油でからっと揚げると殻ごとバリバリと食べられます。その他に、かき揚げ、茹でて殻をむけば、サラダやグラタン、コロッケ、お好み焼き等によくあいます。
色々な料理に使え、旨味が強く、甘味もあり、比較的安価な食材です。

鮭鱒(ケイソン)の種類は一言では中々説明することが出来ません。まず、鮭と鱒を厳密に区別する事さえ難しいとされています。しかし、日常○○鮭と呼ばれているのは銀鮭・紅鮭・白鮭です。その白鮭の中に春から初夏にすこぶる美味なのが「時知らず」なのです。
そもそも、鮭は、秋に産み落とされた卵が川で孵化し海に出ます。3~6年大海原で回遊した後、産卵のため生まれ故郷の川に戻ってきます。この時獲れるのが「秋鮭」です。川をのぼる様子や、またそれを狙う熊の生態など、テレビなどでお馴染みです。お腹には卵を持ち、その分、身の脂分は少なくなっています。
このように本来晩夏から秋にかけて帰ってくるはずなのに、ひょっこり春にたどり着くのが所謂「時知らず」なのです。産卵の季節に達していないので生殖巣が未熟。当然、生殖巣に栄養をとられない為、脂ののりがよく、身が、誠に美味しい。略して「時鮭」とも言われています。
因みに、日本の川に戻ってくるのは白鮭・紅鮭・銀鮭の内、白鮭だけです。
関西は白鮭より紅鮭が好まれますが、春の白鮭「時知らず」は口の中でほどける優しい味です。是非ご賞味ください。

10月の「戻りがつお」に載せましたように、春と秋と違う風味を楽しむ魚です。
「目に青葉 山ほととぎす 初がつお」 さわやかな食味とかおりが身上で、江戸のグルメのひとつだったようです。黒潮に乗って南からやってくるかつおは、餌が豊富な日本沿岸を北上し、房総半島にたどり着くころには、太って脂ものってきますから、江戸っ子達が待ち兼ねたのでしょう。
一方、あっさりしすぎていたり、独特のかおりが苦手という向きもあります。そこで、「かつおのたたき」の出番です。たまねぎ・ねぎ・にんにく・しょうがといったかおりの強い野菜といっしょにポン酢で頂くのは、初がつおならではの調理方法と言えます。
かつおの一本釣りという豪快な漁の他に、曳き縄釣りによる漁もあります。かつおが掛った縄をたぐり寄せ、手で針をはずし、直ちに活け締めし、その日の内に戻り、すぐに出荷するのです。和歌山県のケンケン鰹と呼ばれているのがそれです。
たたきの他には、しょうゆに漬けこんで、唐揚にしたり、腹の部分だけ塩焼きにした「はらもの塩焼き」も、とても美味しいものです。今月ご紹介していますハスイモや季節の野菜といっしょにサラダにしても良いでしょう。
酒盗は、かつおの内臓の塩辛です。特集レシピで酒盗を使った炒め物をご紹介しました。目先が変わった、ちょっと、エスニックな風味でお勧めの一皿です。

刺身・煮込み・バター焼き・スープなど、誠に使い勝手が良く、冷凍庫にいつも欲しい食材です。冷凍技術は飛躍的に進み、尚且つ一番おいしい時を選んで冷凍しています。手軽で便利な冷凍のホタテ貝もお薦めです。
貝類の中でも特に低カロリー・高タンパクで、ダイエットに嬉しい食材です。
ホタテ貝にも目があることをご存知でしょうか。目と言っても、私たちの目とは随分違っていて、光を感じる程度のものですが、実はヒモの部分にある黒い点々がそれで、約80個もあり、100度の広角で認識しているようです。
名画「ヴィーナス誕生」に大きく描かれているように豊穣のシンボルとして扱われたりしてきましたが、現実には、この貝殻の処理は大きな課題となっています。研究の成果として、成分である炭酸カルシウムが持つ消臭効果を利用してシックハウス対応の壁材や塗料などが作られ、意外なところに役立っています。

市場への入荷が多いのは、3月から6月です。
カレイ類は、概ね冬が旬を迎えることが多いのですが、メイタガレイは、春先から初夏が旬なのです。
冬に産卵を終えて痩せていたのが、春に回復し、太って身が厚く、美味しくなってくるのです。
大型で新鮮な物は、刺身にして美味しく、高値で取引されます。
中小型は、唐揚げに向いています。骨は2度揚げにして、骨せんべいとして召し上がってください。
塩焼き・煮付等は定番料理でしょう。
見た目が非常によく似たナガレメイタガレイは、市場では「化けメイタ」と呼ばれています。本メイタガレイより、柔らかく煮付けにされることが多いです。

1996年代に日本癌学会で、フコイダンという水溶性の食物繊維に「制がん作用」があると発表され、そのフコイダンが他の海藻に比べ5~8倍も含まれているのがモズクです。100gあたり6キロカロリーと低カロリーであることも含め、俄然、注目されてきた食品です。
研究はまだまだこれからですが、「血液さらさら」「免疫力アップ」「ピロリ菌除去」「余分な脂肪分排出」などの効果があると言われています。
味付でパックに入った状態で売られていましたが、最近では、収穫・洗浄の後、味をつけないで出荷されるものも増えてきています。
オキナワモズクは太くて大きくさっぱりした味わいで「太モズク」とも呼ばれ、対して細モズクは、細くて小さくネバネバしていて、歯ごたえがあります。
サラダ、長芋やおくらとのネバネバ和え、冷奴のトッピング等生食のレシピもいろいろありますが、加熱してもとても美味しいです。
味噌汁の具、モズク雑炊、てんぷら、卵焼きの具、パスタ、スープ、意外と使い勝手のよいものです。

野菜の多くは、種をまき、収穫し、また翌年、種をまく、を繰り返し栽培しています。多くの消費者も、なんとなくそのイメージをもっています。
ところが、アスパラガスは、一度、種まきをすると、10年は収穫し続けるのです。ちなみに、法人税における減価償却の「生物の耐用年数表」には、アスパラガスは11年と定められているのです。ちょっと、普通の野菜のイメージとは違います。
私達が食用にしているのは、地中から出てくる茎の部分で、晩春から初夏にかけては、一日1回、もっと暑くなってくると、一日2回収穫します。春のアスパラガスの方が、色が濃く、夏出荷されるアスパラガスの方が色が薄いのです。それは、葉の茂り具合によるものです。夏になると、葉が良く茂り、その分、地面から出てくる茎にあたる光が少なくなるからです。
土を被せたり、黒いハウス内での栽培等、遮光を徹底したのが、ホワイトアスパラです。グリーンもホワイトも品種は同じで、栽培方法が違うだけなのです。独特の風味が魅力で、最近では、デパ地下等では、みかけるようになってきました。しかし、手間がかかっている分、価格は、グリーンに比べ高めです。
調理方法は、茹でる、焼く、炒めるなどいずれも簡単においしく頂けます。アスパラガスの根本の方は硬いですが、その硬い部分は、皮をむいてしまえば、おいしく食べられます。アスパラガスは、廃棄率のとても低い野菜といえます。
5月の旬の食材レシピでは、イサキのグリル-アスパラとフルーツトマトのミルフィーユ仕立て-として、見た目にもしゃれた一品を紹介しています。ちょっと目先の変わった一皿として一度お試しください。とってもおいしいです。

碓井豌豆と書き、明治時代に羽曳野市碓井地区にアメリカ合衆国から導入され、その後改良されたむき実用のえんどう豆です。
鹿児島県、熊本県、四国、和歌山県が主な産地です。
実の色は浅く、味はほっこりと甘みがあり、皮が薄く、冷めても硬くなりづらく、又、実と皮が離れにくい、などが特徴です。
関東では余り流通していなくて、関西特有のものです。
関西の豆ごはんは、このうすいえんどうなしでは考えられません。店頭に並ぶのを待ち兼ねたように、初夏を味わうのです。豆ごはん以外では、何と言っても、卵とじでしょう。わずかな期間しか流通しませんから、ゆでて、冷凍保存するのも良いでしょう。
豆ごはんを作る際に、どのタイミングで豆を炊飯器に入れるかですが、最初から入れる、途中から入れる、又、別茹でして最後に混ぜる等、好き好きですが、最初から入れた方が豆の色は悪くなりますが、味が濃く、おいしいです。
剥いた鞘からだしを取り、それで、炊くとおいしさひとしおです。一度お試しください。

実りの秋を象徴するような野菜ですが、実は、5月中旬ごろにもなると、顔を出し始めます。貯蔵で冬を越えた物もぼちぼち底をつき、この新サツマイモと交代する訳です。
5月・6月は新サツマイモの中でもはしりと言えます。
特徴は、香りが高く、甘味が少ない、と言う事です。
秋のサツマイモは、その甘みのため、おかずの材料としての活躍の場が少なく、どちらかと言うとおやつ感覚のレシピが多いのですが、新サツマイモは甘味が少なく煮崩れしにくい特徴から、断然、利用範囲が広がってくるのです。天ぷらはもちろんのこと、煮込み料理、サラダ、きんぴら等、じゃがいも料理の目先を変えたヴァージョンで簡単にお使いいただく事が出来ます。
セルロース・ペクチンなど食物繊維が豊富なことは有名ですが、便秘を解消させる作用だけでなく、血液中のコレステロールを低下させる作用や血糖値をコントロールする働きもあります。また、βカロチン、ビタミンB1、ビタミンC、ビタミンEなども、バランス良く含まれていて、消費者の健康指向に伴い、良さが見直されてきています。
甘味がどうも、とおっしゃる方々には、是非、香り高い新さつまいもをお料理に取り入れて下さい。

別名リュウキュウとも言い、芋の部分は食べずに、葉柄(ズイキ)の部分のみ食べる高知県の伝統野菜です。
きれいな薄緑で、皮をむくと、中は白く、小さな穴があり、スポンジのような断面です。
皮をむいて、生のままでも食べられますが、お好みで、さっと湯通しの後、少しもんで、あくぬきします。
他の食材とあわせて、酢味噌やマヨネーズであえたり、酢の物、サラダにと、また、刺身のツマ、味噌汁、炒め物、など、色々試してみて下さい。加熱してもしゃっきり感が残りますので、シチュウの具にも面白いです。
味がなく、どんな食材とも相性が良く、5月頃から7月頃の最盛期には、お手軽な値段となり、「もう一品」と言う時にも重宝です。
シャリシャリとした食感が夏にぴったりの野菜で、繊維質が豊富な、ヘルシー食材です。

「フルーツトマト」という品種・分類は無く、農林水産省による統計はありませんが、益々、その売り場面積が広がっているのが実感です。
フルーツトマトと言えば、まず、その糖度の高さが特徴でしょう。普通のトマトが5度~6度に対して、フルーツトマトは概ね8度~10度あります。基準があるわけではありませんが、生産者側のこだわりで出荷しているのです。只、糖度だけのお話だと、レモンの糖度は、7度~8度程度。酸味が強い為、口に含んだとき、酸っぱい!と感じる訳で、要するにバランスの問題です。フルーツトマトは、甘さだけでなく、旨みや、酸味が一体となって「甘くて美味しい」野菜となった訳です。
さすがに生食が主流です。水分を極度に抑えた栽培の為、皮が厚いですが、その分、傷みにくいのも特徴です。

全国らっきょうサミットというのがあります。鹿児島県・宮崎県・高知県・鳥取県・徳島県・福井県の産地の方が集まって、勉強会・情報交換をする場となっていますが、今年は4月24日に大阪市で開催され、翌日ここ本場で、市場の動向等の視察が行われました。産地ではなく、消費地での開催は初めてです。
主な出荷地はこのサミット参加の各県です。
スーパーなどで販売されているのは「洗いラッキョウ」と「根付ラッキョウ」があります。
洗いラッキョウは根と茎を切り、切ったところから芽が出ないように塩水で洗ったものです。
根付ラッキョウは茎を短く切りそろえ、軽く土を落としただけのものです。洗いラッキョウは手間なく漬け込むことが出来、根付ラッキョウはよりしゃきしゃき感があるものに仕上がります。
また、酢漬け・塩漬け以外にも根付ラッキョウで、てんぷら・味噌和え・サラダ・冷奴のトッピングの他、是非、焼きラッキョウをお試しください。フライパンで炒める・網焼き・ガスコンロのグリルなど。みりん醤油をつけてお召し上がりください。意外なおいしさです。

ここ本場へは熊本からの入荷が圧倒的に多いのですが、そのピークは5月です。日本の種苗会社が開発し、ネーミングの由来は「作る・売る・買うのに安心ですメロン」から。メロンを食べる際、芯の部分を除くので、「あんしんですメロン」から「しん」を除いてアンデスメロンとなったとか。
庶民派の価格帯でありながら、高級メロン似た外観と食味で人気があります。最近は、センサーの導入により糖度の安定がはかられており、益々美味しくお届けできるようになりました。他のメロン同様、食べる2~3時間くらい前に冷蔵庫で冷やすのが良いのです。くれぐれも冷やしすぎにはご注意ください。

西から、南からスイカの季節がやってきます。5月ともなれば、熊本では最盛期を迎えます。
季節が進むにつれ鳥取県、次に石川県と、東へ北へと出荷地が変わっていきます。
今の時期は、ハウス栽培ですが、メロンのように、吊るして栽培しているこだわりの農家もあります。
全国有数の出荷量を誇る熊本県ですが、4月の熊本地震で、すいか農家も大打撃を受けました。報道によれば、地震による被害で出荷不能になったものもありますが、これから出荷のピークを迎えようとしています。機械が使えず、自動出荷作業が出来ない選果場や、ボイラーを使えない中で、温度管理を行うなど、きびしい状態ですが、それでも、おいしく実ったものから、手作業で出荷を再開している地域も沢山あります。2度にわたる震度7の地震で大きな被害に遭いながらも懸命に作業を続けるスイカ農家の皆さんにはくれぐれもお身体に気をつけて、頑張っていただきたいです。

5月から夏にかけてがメロン本来の旬の季節。
きれいな網目の高級果物アールス(マスク)メロン以外にもアムスメロン・アンデスメロン・タカミメロン・クインシーメロン等の出荷が本格的になってきます。
気温の上昇とともに、水分が欲しくなってきますが、果物は水分補給にもってこいなのです。メロンはその中でも特にカリウムの量が多く、水分の摂取ばかりでなく、そのバランスの調節をする働きもあり、利尿作用やむくみ解消にも効果的です。
ハウス栽培のアールスメロンは一年中店頭に並びますが、他の品種はいよいよこれから出荷が増えてきます。色々なメロンの食べ比べをしてみてください。